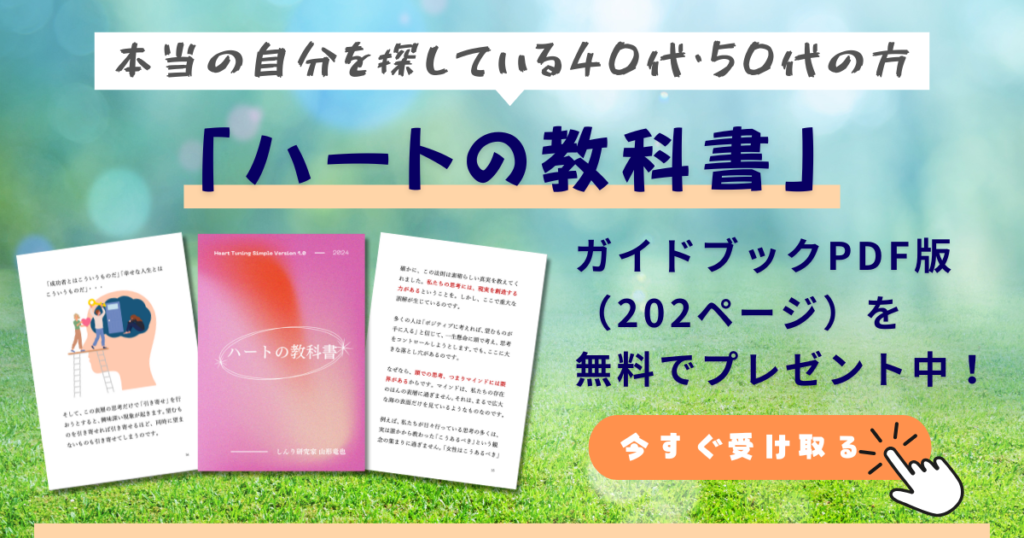「バウンダリーは線を引くことでしょ?でも、ワンネスはすべてがひとつ……って、それ、矛盾してない?」
そう感じたことがあるならば、これはあなたのための記事です。
ハートの音色を奏でよう!Heartist 心理セラピストの山形竜也です。
今回の記事では、バウンダリー(境界線)とワンネス(すべてはひとつ)をどう統合すればいいのか、Heartistの視点からやさしく解きほぐしていきます。
「バウンダリー(境界線)とワンネス(すべてはひとつ)ってどっちが正解なの?」
「この2つを状況によって使い分けるって、できるものなの?」
「ワンネスが真実なら、なぜバウンダリーが必要なの?」
このような疑問にお答えします。
★この記事のポイントは・・・
- バウンダリーとワンネスは矛盾しない
- 「どちらが正しいか」ではなく、「どちらも必要」
- 両方を感じながら、都度“調和点”を探していく感覚
バウンダリーとワンネスの関係にモヤモヤしているなら、この記事がきっとヒントになります。答えは“どちらか”ではなく“どちらも”。ぜひ最後まで読んでみてください。
バウンダリーとワンネス、どっちが正しいの?
バウンダリーって、相手と健全な境界線を引くこと。
でも、“すべてはひとつ”っていうワンネスの考えもある。
……これって矛盾してない?
こんな風に感じたこと、ありませんか?
たとえば、誰かの悩み相談を聞いているうちに、自分の気持ちが沈んでしまったとき。
「これは相手の感情なのに、なぜか自分が重たくなっている…」と気づいてモヤモヤ。
あるいは、心の学びを続ける中で、「もっと相手と一体になることが愛なんだ」と信じて、どんどん自分をすり減らしてしまった経験。
バウンダリー(境界線)を大切にするという考えと、ワンネス(すべてはつながっている)というスピリチュアルな考え。
まるで正反対に感じてしまうこの二つ。
「私は自分を守るべきなの? それとも、すべてを受け入れてひとつになればいいの?」
そう悩んでいる人は、実はとても多いのです。
特に、感受性が高く、共感力に優れた女性たちは、この矛盾に強く引っかかります。
そして、頭ではどちらの考えも正しい気がするのに、「じゃあ実際、どうすればいいの?」という答えが出ないまま、苦しさだけが残ってしまう。
でも、ここには“ある大切な視点”が抜けているのです。
それは、バウンダリーとワンネスは、そもそも「どちらかが正しい」「どちらかを選ぶ」ものではないということ。
むしろ、この2つは、健やかな人間関係や内面の統合にとって欠かせない“両輪”なのです。
では、詳しくみていきましょう!
バウンダリーとは?自分を大切にする線引き

バウンダリーとは、自分と他人の間に引かれる「心理的な境界線」のこと。
でも、それは“拒絶”や“壁”ではありません。
むしろ、自分の気持ちやエネルギーを守りながら、相手と健やかに関わるための線引きです。
たとえば——
- 「今日は疲れているから、ひとりの時間を優先したい」
- 「その話題は、今の私には少し重たすぎる」
- 「私はこう感じているけれど、あなたはどう?」
こうした言葉を素直に伝えられることが、バウンダリーを持っている状態です。
しかし、多くの人が「嫌われたくない」「空気を悪くしたくない」という思いから、本音を飲み込んでしまいます。 でもそのたびに、少しずつ“自分の輪郭”が曖昧になっていくのです。
そして最終的には、
- 相手の感情に巻き込まれる
- 嫌なのに断れない
- 頼まれたら無理してでも応じてしまう
という“共感疲れ”や“自己喪失”が起きてしまいます。
バウンダリーは、そんな自分を守る「愛のガードライン」。
それは冷たさではなく、むしろ「私はここにいるよ」という自分への誠実さです。
相手との健全な距離感があるからこそ、本音で話せる関係が育ち、
本当の意味で「安心してつながれる場」が生まれるのです。
ワンネスとは?本質でのつながりを思い出す感覚

ワンネスとは、「すべてはつながっている」という本質的な感覚のこと。
物質的な分離の奥に、目に見えない“いのちのつながり”や“意識の一体性”を感じる在り方です。
でも、それは“全部ひとつになろう”とする努力ではありません。
違いを持ったまま、深い部分ではすでにつながっていることを感覚が知っている—— それが、ワンネスの感覚です。
たとえば——
- 空を見上げたときに、ふと「私はこの世界の一部なんだ」と感じるとき。
- 大切な人の涙に触れて、自分の心も震えたとき。
- 言葉を交わさなくても、通じ合っていると感じる瞬間。
こうした体験の中に、ワンネスは自然と立ち現れます。
つまりワンネスとは、自分を消すことではなく、「私はここにいる」と感じながら、同時に「あなたもここにいる」と感じられる心の状態なのです。
ところが、この感覚を頭で理解しようとすると、
「じゃあ自分の意見や感情を手放した方がいいのかな?」と、
気づかぬうちに“自分をないがしろにする”ような捉え方になってしまうことがあります。
大切なのは、“私”を大切にしたうえで、“私たち”を感じること。
そうしたワンネスの感覚は、無理に追い求めるものではなく、
むしろ、ハートが静かに開いたとき、自然と訪れるものなのです。
バウンダリーが「私の輪郭」を守るなら、
ワンネスは「その輪郭の奥にある、本質的なつながり」を思い出させてくれます。
バウンダリーとワンネスは矛盾しない? 本当の関係性とは

一見すると、バウンダリーとワンネスは正反対に見えるかもしれません。
片方は「線を引くこと」、もう片方は「すべてはひとつ」。
でも、この二つは対立するものではなく、むしろ“順序と層が違う”だけの、補い合う関係なのです。
たとえば、地上に暮らす私たちは、感情を持ち、肉体を持ち、それぞれの価値観や体験を抱えています。 だからこそ、まずは「私はここにいる」「あなたはそこにいる」「私は私、あなたはあなた」という健全なバウンダリーが必要です。
バウンダリーは、自分を守る“輪郭”であり、
相手との「ちょうどいい距離」をつくるための出発点なのです。
そして、その安全な輪郭の内側に、ハートがやさしく開き始めたとき。
そこではじめて、ワンネス——つまり、「違いを超えて、私たちは深いところでつながっている」という感覚が自然と芽生えてきます。
言い換えれば、
- バウンダリー=私が私であることの確かさ
- ワンネス=私でありながら、あなたと響き合う喜び
この2つは順番に体験されることで、統合された“真のつながり”へと育っていくのではないかと感じます。
もし、バウンダリーを持たずにワンネスを目指すと—— それは、まるで
“自分という色を消して、相手の色に塗り替わろうとする”ようなこと。
結果として、自分を失って苦しくなったり、無理を重ねてしまったりするのです。
逆に、バウンダリーだけを意識しすぎると—— 心が閉ざされ、孤立感や寂しさが強まってしまいます。
だからこそ、「どちらが正しいか」ではなく、「どちらも必要」。 そして何よりも大切なのは、 “自分の心が今、どちらを求めているか”に正直であることなのかもしれません。
境界線を持つことと、つながりを感じること。
そのどちらもが、“私らしい人生”を奏でるために欠かせないのです。
【実例で理解】バウンダリーとワンネスが共に必要な3つのシーン
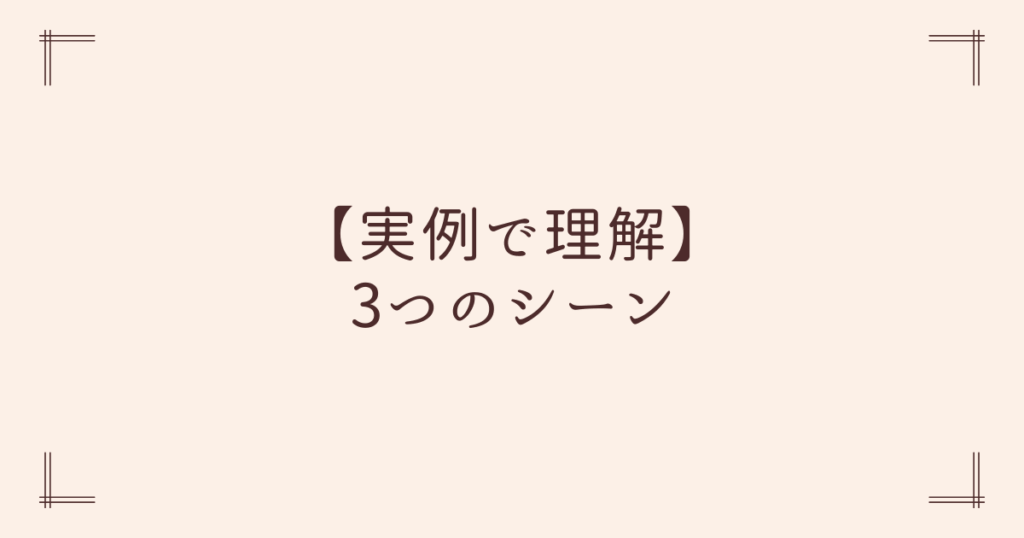
「なるほど、バウンダリーもワンネスも大事なのはわかった。でも実際の生活では、どう使い分ければいいの?」
そう感じる方のために、ここでは日常の中でよくある3つの場面を通して、バウンダリーとワンネスのバランスの取り方を具体的に見ていきます。
◆ シーン1:友人の悩み相談を受けたとき

たとえば、親友がつらい出来事を話してきたとします。
バウンダリーがないと…
相手の感情に巻き込まれ、自分まで落ち込んでしまう。
「私が何とかしてあげなきゃ」と背負いすぎてしまい、苦しくなる。
ワンネスだけを求めると…
「すべてはつながってるから大丈夫」と安易に慰め、相手の“今ここ”の感情を置き去りにしてしまう。
統合のポイント:
「あなたの気持ちがわかるし、一緒にいてあげたい。でも、あなたの感情まで私の中に取り込む必要はないんだよね」という在り方 → まるで“となりに座って一緒に感じているけれど、自分の椅子にはしっかり腰かけている”ような関係性。それが、ほんとうの寄り添い方だと思います。
◆ シーン2:パートナーや家族とのすれ違い

たとえば、意見が食い違って険悪になったとき。
バウンダリーがないと…
相手の反応や言葉をすぐに“自分のせい”と受け取ってしまい、「どうせ私はダメだ」「私が悪い」と自己否定モードに入りやすくなる。バウンダリーがないことで、他人の感情や評価がそのまま“自分の価値”と感じられてしまうのです。
ワンネスに偏ると…
「私たちは一心同体なんだから、わかってくれて当然。なのになぜわかってくれないの?」という思いが無意識に働き、相手への期待が膨らみすぎて衝突が深まってしまう。
統合のポイント:
「私は私の感じ方を大切にしながら、あなたの考え方にも耳を傾けたい」という在り方 → まるで“別々の椅子に座っているけれど、同じテーブルを囲んでいる”ような関係性。違いを尊重しながら、関係を深めることができそうですね。
◆ シーン3:グループやコミュニティでの場づくり

たとえば、ファシリテーターが主宰するワークショップや講座で、参加者の一人が涙を流しながら自己開示したとします。
ファシリテーターがバウンダリーを持てないと…
「何とかしてあげなきゃ」「この場を助けなきゃ」と過剰に反応し、自分が場をコントロールしようとしてしまう。結果、ファシリテーター自身が感情に巻き込まれ、場のバランスを崩してしまう。
ファシリテーターがワンネスに傾きすぎると…
「すべては完璧だから、ただ見守ればいい」と何もしない選択をし、結果的に自己開示した参加者が孤立してしまうことも。
統合のポイント:
「今ここで私ができることは、安心して話を聞くこと。感情に飲み込まれず、でも心を開いて関わる」という在り方 → 自分の立ち位置を保ちながら、場に調和をもたらす。その“意識ある関与”が、安心とつながりを育てる鍵になります。
このように、バウンダリーとワンネスは“使い分ける”というより、両方を感じながら、その都度“調和点”を探していく感覚に近いのかもしれません。
Heartistとは、自分という音色を大切にしながら、他者と調和を奏でようとする存在。
だからこそ、「境界」と「つながり」の両方に耳を澄ませながら、心地よいバランスを見つけていくことが、何より大切なのです。
Heartistの視点:“私”という音色を持ちながら、世界と響き合う

ここまで読み進めてくださったあなたはきっと、ただの「正しさ」や「理論」ではなく、
自分らしく、でも孤立せず、誰かとやさしくつながっていたいと感じている方だと思います。
それは、まさにHeartistの生き方そのものなんです。
自分の内側にある感情、感覚、願い、欲求を大切にしながら、 他者の音にも耳を傾け、共鳴しながら調和を生み出していく。
つまり、Heartistとしてハートの音色を奏でながらその上で・・・
- バウンダリー=私の音色を守ること
- ワンネス=あなたと響き合うこと
この両方を大切にすることが、Heartistの世界観の中心にあります。
そして大切なのは、それを「上手にやろう」とするのではなく、
まずは“聴くこと”から始めるということ。
たとえば、
- 朝、目が覚めたときに「私は今、どう感じてる?」とハートに問いかけてみる。
- ふとした場面で「今、この人の言葉をどう受け取ってる?」と内側を感じてみる。
そのひとつひとつが、 あなたという楽器を“チューニング(調律)”する行為なんです。
チューニングされた楽器は、自然とまわりと調和します。 誰かより強くなくていい。完璧じゃなくていい。 でも、自分の音を持っていることで、どんな場でも、“あなたらしい音色(ねいろ)”を奏でることができると思うんです。
Heartistとして生きるとは、 「自分を守る」ためのバウンダリーと、 「つながる」ためのワンネスを、 どちらも排除せず、どちらも大切にする勇気を持つことなのかもしれません。
それは時に難しく感じるかもしれない。 でも、自分のハートに正直である限り、 あなたの音色は、ちゃんと世界と響き合っていけるはずです。
どうかその響きを、あなた自身が信じてあげてください。
さいごに:本当のつながりは、“境界”の先にある
バウンダリーとワンネス。 一見、正反対に見えるこの2つの概念は、実はどちらも「本当のつながり」を育むために欠かせないものでしたね。
- バウンダリーは、自分を守り、自分を尊重するための輪郭。
- ワンネスは、その輪郭の内側から響き合う、深いつながりの感覚。
境界線を持つことは、決して冷たさや拒絶ではありません。むしろ、それは自分を大切にしながら、他者とも誠実につながっていくための土台なのです。
そしてその土台があってこそ、ワンネスという“見えない共鳴”は、心から安心して感じられるようになる。
「私は私でいていい」
「そのままのあなたとも、つながっていられる」
——その両方を許せたとき、人はようやく自由に、そしてやさしく、人生を奏で始めることができます。
Heartistとして生きるあなたへ。
どうか、自分の音色を否定せず、そして誰かの音色とも調和することを恐れずに、
あなたらしいハーモニーを、この世界に響かせてください。
その響きが、また誰かのハートに触れ、新しい共鳴を生んでいきます。
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。
👇 Heartistについてもっと知りたい方へ
あなたもハートの音色を奏でたいならば、こちらもご覧ください▼
>> Heartist マニフェストを読む